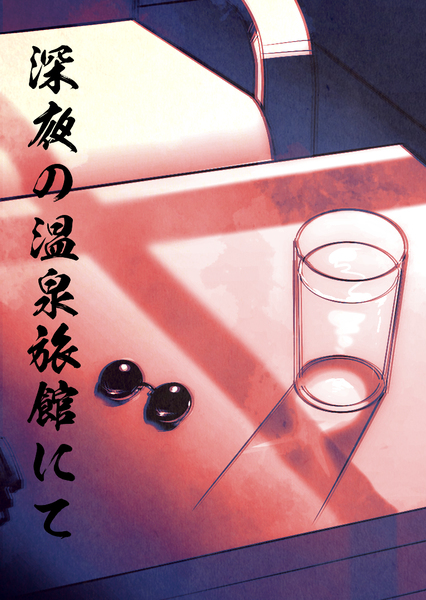『一睡の雨』
それは糸のように、細く、白く、長く。
たつ、たつ、と音がする中を駆け足で進む。今日は大丈夫だろうと謎の自信があったのに、見事に外れた。つまりそう、傘がないのだ。
「うわー! 待ってくれよぉ!」
容赦なく激しくなってくるのを肌で思い知りながら、焦る心のままに足を動かす。あっという間に映し出されていく波打つ空をばちゃりと散らし、腕は額、より正確に言えば眼鏡のすぐ上にあてて少しでも視界を確保する。
そんな努力の甲斐もあり、世界が薄灰色に覆われて幾ばくもしないうちに目当ての建物に辿り着く。ひさしなんてない出入り口、ガラスのはまった引き戸をがらがらと開けて室内に飛びこむ。
「おー、来たか」
「とりあえず拭けよ。そのへんみーんな濡れっちまう」
声と共にタオルが投げられた。
「あざっす。すんません」
使い込まれた大きめのタオルはどことなくくたびれ、うっすらと色付いている。すでに湿っているのは先に同じように滴を拭ったものがいるからだろう。それでも文句は言わず、おとなしく頭からがしがしとこするように拭いていく。逆さまに降られた足元は特にひどかったので、置きっぱなしになっている誰かの予備のズボンを拝借する。腰回りのゆるさはベルトで調節した。
「これじゃあ今日は無理っすかねー?」
軽くしぼったタオルと脱いだズボンをハンガーにかけ、首を振る大型の扇風機の風があたる位置に干す。生乾きになってしまうのがわかりきっているのであまりよくないのだが、仕方ない。ぐっしょりと濡れたままよりはずっといい。
「いや、たぶんすぐ止むだろ。夕立じゃないか?」
「梅雨もまだだぜ?」
「ならなんて言うんだ?」
「さあなぁ」
そんな先輩たちの会話を聞きながら、窓に寄る。軽く引きずった折り畳み式の椅子を広げ、ぽすんと腰を下ろした。
室内の明かりを受けた雨はいまだ勢いよく降り注いでいる。風で少し斜めに線を引くさまは、定規をあてているかのようだ。
 きらきらと白く光りながら引かれる、白い線。屋根を通して届く、ざーざーと強い音。
きらきらと白く光りながら引かれる、白い線。屋根を通して届く、ざーざーと強い音。
細っこいのに芯がある。
目からの情報と耳からの情報が噛み合わない気がして、思わずくすりと笑った。
「とりあえず待ってみるか。もう三十分くらいで上がらないなら、今日は諦めるぞ」
「さすがに仕事にならねえか」
「そういうこった」
今日この後の方針も決まったようだ。今のところはやることがないということで、組んだ足に肘をついて顎を支え、そのままぼんやりと外を眺める。
ざーざー、ざーざー。
薄暗さと一定のリズムに楽な姿勢は、どうしても眠気を誘う。昨日ちょっぴりだけ寝るのが遅かったことも、それに拍車をかけた。
「おーい、
「うーす……」
名前を呼ばれたことでそこだけは耳には入ってきたものの、その内容は右から左。かろうじて返事はしたものの、それだけだ。
暑いくらいのぬるさも薄まり、うたた寝にはちょうどよいくらい。
激しかった雨もあっという間にひそまり、今や名残を惜しむように長く垂れるのみ。半ば以上を夢の世界に向かわせた者の背を押して、どっぷりと全身を浸からせようとしているかのようだ。
あぁ、こりゃあ無理だわ。
話し声と物音をBGMに、魅力的すぎるそのお誘いに身を任せた。
「うーん……」
椅子に座ったまま寝るというのは、体に結構な負担がかかる。両手を上げて伸びをすると、ぱきっと関節の鳴る音が響いた。首を回せば、これまたいい音がする。
「ありゃ?」
見回せばそこはさっきまで自分がいた場所ではなく、さりとて知らぬ場所でもない。
霞がかった頭と視界に入ってくるのは、飾り気のない実用的かつ簡素な長机と、自分が今腰掛けているのと同じ折り畳み式の椅子。
そして。
「だから別に好き嫌いの問題じゃないし、第一、僕が好き嫌いしたってヒロには関係ないじゃんか」
「ちっこいよりでっかいほうが絶対いいと思うんだけどなー」
「ならジイちゃんはどうなのさ。僕より身長ないよ」
「ジイちゃんはジイちゃんだから~」
「理由になってない!」
「まぁまぁ、二人とも落ち着きなされ」
仲良く喧嘩する白と黒の
見飽きるほどに見慣れた光景だ。
窓の外の
「何? どうかしたの、職長?」
ちょうど煎餅を食べ終え、指をぺろりとなめたユン坊が声をかけてくる。
「あ! ショクチョー、はよっス!」
「だいぶんお疲れのようですのぅ」
ジャーキーをかじりながらのヒロに、湯飲みの中身をすするジイ。
「お、おう……」
いつも通りの彼らの姿に、ようやく今の日常が意識に染みてくる。
そうだ、ここは地獄だ。
自分は死んで、喚ばれ鬼となり、今がある。
どれだけ細かろうとその長い糸は過去と現在を繋ぎ、きっと未来へ繋がっているのだろう。今の自分に、本当に
「オレ、悪くない!」
「仲がいいのう……」
「だーもう! うるせー!」
感傷に浸る暇なんてない。でもきっとそれでいい。
「休憩終わり! オラ! 仕事に戻んぞ!」
意識を切り替えて立ち上がる。
窓の外は見ない。
仮設事務所の扉を開ければ、現実がそこに広がっているのだから。

小話

Copyright © ZIGOKU’S FOREMAN