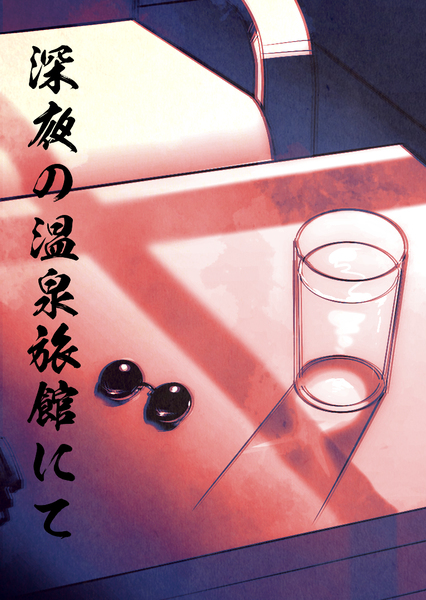『酒は飲んでも呑まれるな』
注文をする声と取る声が、表から裏へ、裏から表へと伝えあう声が、今日も掛け合いをしている。そんな中でも埋もれることなく、客同士が、あるいは客と店員が会話を楽しんでいる。もちろん店には一人で飲みたいモノも来るが、店の側もそこのところはちゃんと心得ている。そんな客には端の席をすすめるし、必要以上に話しかけることもしない。
酒処『やなぎあめ』はそんな風に、今日もそこそこに繁盛していた。
「えぇっ!? ねぇの!?」
店内に響き渡るほどの大きな声で、ついミヅチは悲しみの声を上げてしまった。
「悪いねぇ旦那。でもほら、今日はこれもオススメなんで」
「ううー……」
材料が終わってしまったという一番お気に入りのメニューの代わりに、馴染みの店員がすまなさそうに勧めてくれたものを注文する。
「まぁ、ねぇってもンはしょうがねぇか。店がそれだけ繁盛してるってぇことだし、よかったじゃねぇか」
「そう言ってもらえると、こっちも助かりますよって」
お通しをつつきながら、今日も他愛ない会話を始める。料理もほどなく完成し、酒も揃えばもうそれだけで満足というものだ。
「お、今日のタネは大根も入ってるのか!」
「そうなんすよ。ちょうど新鮮な野菜が入荷したんで、今日は久しぶりに入りやした」
頼んだ料理はおでん。大根の他にちくわや卵、さつま揚げ、肉に巾着と、なかなかのボリュームだ。鬼にとって野菜は不調を引き起こす食べ物であるが、それでも喚ばれ鬼の間では需要が絶えることはない。不調になるならそれを治せればいいじゃないかと意欲を燃やし、薬まで開発されている。ここのように野菜を提供する店では、セットで薬も準備されているのが常だ。
味のよく染みた大根を箸で割り、口に運ぶ。やわらかくなりすぎない程度に歯ごたえを残した大根は、今も昔も大変に美味だ。おでんと言えば冬と思いがちだが、地獄に四季なんて期待するほうが無駄である。基本的には暑いか寒いかの二極であり、それならば食べたい時に食べたい物を食べるのが正解というものだ。
ミヅチがそんな正しい幸せを文字通り噛みしめている間にも、店には新しい客がやって来る。その客も
大柄な客の額には立派なツノが生えており、鬼であることが窺える。筋骨隆々の大柄な体を見せつけるように上半身はベスト一枚、そう遠くない席にどかりと腰掛け、ゆったりめのパンツを履いた足を組んだ。その拍子に鳴ったかちりという音で、金環の存在が知れた。
「いらっしゃい」
「おう。来てやったんだからありがたく思え」
体躯に合う低いだみ声で、がははと笑う声まで大きい。既にどこかで飲んできたのか、やけに陽気で態度も尊大だった。
そんな客も珍しくないのだろう、ミヅチの相手をしていた店員は鬼の前に立つと笑顔で対応を始めた。のだが。
「あぁ?
「すみません、うちは『ナマなし』でして」
「ンだよ! 飲み屋のクセに肉がねーとか、シケてやがるな!」
鬼が床に唾を吐く。べしゃりと落ちた唾はテーブル席の客の足の近くまで飛沫を散らし、その客は嫌な顔をして席を立った。店内を回っていた店員が慌てて会計に向かい、頭を下げる。
鬼のほうはまったくの他人事で肉料理を注文し、酒をあおっている。かと思えばその酒にも、不味いから別のを持ってこいなどと文句を言う。
そんな鬼の様子は明らかに店の空気を悪くし、客はその数を減らしていく。
はっきり言って面倒くさい、迷惑で厄介な客だった。
ミヅチも席を立ちたい気持ちはあるのだが、まだ飲み食いは終わっていないし、一番近くにいる自分が動けば鬼の視線と興味が自分に向きやしないかと不安でもあった。自分より大きい体というそれだけで本能的な恐れがあるのに、生粋の鬼ともなれば誰かを傷つけることに何の
しかし災難なのは店のほうだ。相手をする馴染みの店員も困ったような雰囲気だし、帰る客に頭を下げて詫びる店員だって自分たちのせいではないのに可哀想だ。売り上げに響いていることも想像に難くない。
助けてくれとか、言われたわけじゃねぇし……。
何とかしてやりたい気持ちだけあっても、それが出来るとは限らない。いたずらにコトを大きく、より面倒にするだけかもしれない。引っ掻き回すだけなら、何もしないほうがいいのではないだろうか。
ミヅチは板挟みの気分まで味わいながら、誰にするともなくそんな言い訳を心でした。
「ったく、これだから喚ばれもんはよぉ」
いつもならもう一品、もう一本なのだが、今日はさすがにおれもお勘定かなと思う頃、その言葉がミヅチの耳に飛び込んできた。
「あ?」
思わず鬼のほうに顔を向けてしまう。幸いなことに鬼はミヅチのことは気にせず、店員に向けて悪態をつく。
「ナマは食わねーのに、ヘーキで野菜とかいう毒は食らう。味は薄いし酒もクソまずいじゃねーか」
「いやその……すみません」
誰からも反論がないのをいいことに、鬼は好き放題に店や店員たちを貶める言葉を連ねていく。
不喜区にあるこの店は地域柄、喚ばれ鬼が多く働いている。店主も喚ばれ鬼であり、同類たちのための店という色が強い。店先に『ナマなし』の但し書きをしていることもそうだ。もちろん店である以上他のモノたちの来店もあるが、そういう店であると了承した上でのことというのが条件だ。
「まったく、この店はハズレもいいところだぜ」
よく知らずに来店したにせよ、自分に合わないならこの店に二度と足を運ばなければいいだけ。こんなことを言う必要はまったくない。
「すみま――」
「よォニイちゃん! ずいぶん威勢がいいじゃねぇか!」
謝罪を繰り返す店員を遮って、ミヅチは鬼に声をかけた。
「おれぁニイちゃんみてぇなの、キライじゃないぜ?」
喚ばれ鬼には珍しいツノ、焼けた肌の色がミヅチを生粋の鬼のように見せている。大柄な鬼は、自分がたった今まで馬鹿にしていた喚ばれ鬼だと気付かない。
ミヅチは軍手を置いて席を立つと、鬼の肩を叩く。
「一緒に用足しに行こうぜ」
ニヤと笑えば、鬼もニッと笑った。ミヅチも決して小柄ではないのだが、立ちあがった鬼と並べばその体格差は明らかだ。
だが、今のミヅチはもうそれを恐れない。いや、恐れはある。ただ怒りがそれを上回った。
「おっと、そっちじゃねぇって」
店の奥に足を向けた鬼を引きとめ、くいと親指で外を指し示す。
「こんなシケた店なんか、いたかねぇだろ?」
「はっ! それもそうだ!」
嘲笑う鬼と連れだって外に出たミヅチは、居酒屋横丁を抜け、居住区を過ぎ、どこまで行くんだと不満と不審を溢した鬼を適当にあしらいつつ、どんどんと寂しいほうに向かう。
不喜区は本来、
ミヅチが足を止めたのは、そんな開発途中とも呼べないあたりだった。
「こんなところまで来る必要あったのか? 何かあっても、だーれも助けちゃくれねぇぜ」
「別にやりあおうってわけじゃねぇって」
くすんだ白と焦げついた黒の隙間から顔を出すちろりちろりとまばらな芝生のような火は絶えず、時に間欠泉のように火柱が上がる。楝の木だけがぽつんぽつんと生えているのが、ちょうど闘いの場のような空気を作っていた。
「そんなら、なんだってんだぁ!?」
やる気もあらわに拳を打ち鳴らす鬼をよそに、ミヅチは足下を確かめるように歩き回っていたが、この辺かな、とようやく足を止めて鬼を振り返った。
「言っただろうが。用足しだって」
この辺かな、と呟くミヅチの様子は、鬼の目にまったくの自然体に映る。争いを好む様子でもなく、恐れるでもない。自分より貧相といっていい体つきなのに、身構えることもなく落ち着いているというのは彼にとっては異様なことだった。
「あぁでもこれじゃあ、丸見えになっちまうなぁ?」
朱に近い濃さのツノを持つ鬼は気負いない動作で足を上げると、よっ、と軽い掛け声と共に振り下ろした。
轟音がした。地面が揺れ、木が倒れた。地を這う仄火が一瞬消え、反比例するように火柱が烈しさを増した。
「ニイちゃん、タッパあるからなぁ。足りねぇかな?」
煙幕のように舞い上がったものが収まると、地が穿たれていた。広く深いその穴は、一人くらいは簡単に隠れてしまえそうなほど。
何気なく足を上げ、下ろした。動作としてはそれだけだ。それだけで、これほどの穴を作り、己を誇示するでもない。
それは彼の常識には当てはまらないことだった。
一人分しか掘れなかったとぼやきながら、確かめるように穴のふちをとんとんと踏んでいるその背が、途轍もなく大きく見える。
得体が知れない。
「ニイちゃん、先でいいぜ」
親しげに笑いかけてくるその口が、ガバリと開いて自分を喰らうのではないかと、途方もない妄想に取り憑かれそうになる。
どうしたと貼り付けたような笑顔のまま近づいて来る様子がうすら寒く、覚えず下がろうとして尻餅をついたところで、やっと足の震えを知った。
ほんの微かな足音で、ばさりと外套を翻してしゃがんだ
捕まった。そう感じた瞬間だった。
「あーあー、ニイちゃん。それはここじゃあねぇだろ?」
絶望感と場違いな解放感を同時に味わいながら、彼は意識を手放した。
「悪ぃ! 中座しちまってよ!」
がらがらと引き戸を開ける音と元気な声に、店の者たちは一斉に体を向けた。
「旦那ぁ!」
「おー、災難だったなぁ」
ミヅチはひらりと片手を振りふり応えると、何事もなかったかのように定位置に戻った。待っていたのは置いた軍手と、中身が残ったままのグラス。そして馴染みの店員の申し訳なさそうな顔。
「旦那……すみません」
帽子を取って頭を下げる店員に、ミヅチはにっかと笑いかけた。
「
眉を八の字にし、ミヅチも謝罪を口にする。
「同調するためだったたぁいえ、おれもひでぇこと言っちまったな……」
「そんな! いいんスよ。おれら皆、わかってます!」
謝罪合戦になりそうだった空気は、店にいた全員が頷き同意することで払われた。
「今日は店のほうで勉強させてもらうんで、じゃんっじゃん飲んでいってくださいって!」
「えっ!? いいのか!?」
いやぁそんなつもりじゃなかったんだけどよぉなどと言いつつも、感謝され煽てられたミヅチは、にへらにへらと頬を緩ませてしまう。
「ささっ、旦那! 乾杯の音頭、お願いします!」
「おうよ!」
と元気よく答えたものの――。
「ちょっと待ってくれ。なんか、立てねぇや……」
すわ怪我でもしたのかと寄って見れば、何のことはない、まるで貧乏ゆすりがごとく、足が震えているのだった。
「なんすか、それ!」
どっと明るい笑いに包まれる店内で、ミヅチはたははと小さく笑って頭をかいた。

小話

Copyright © ZIGOKU’S FOREMAN